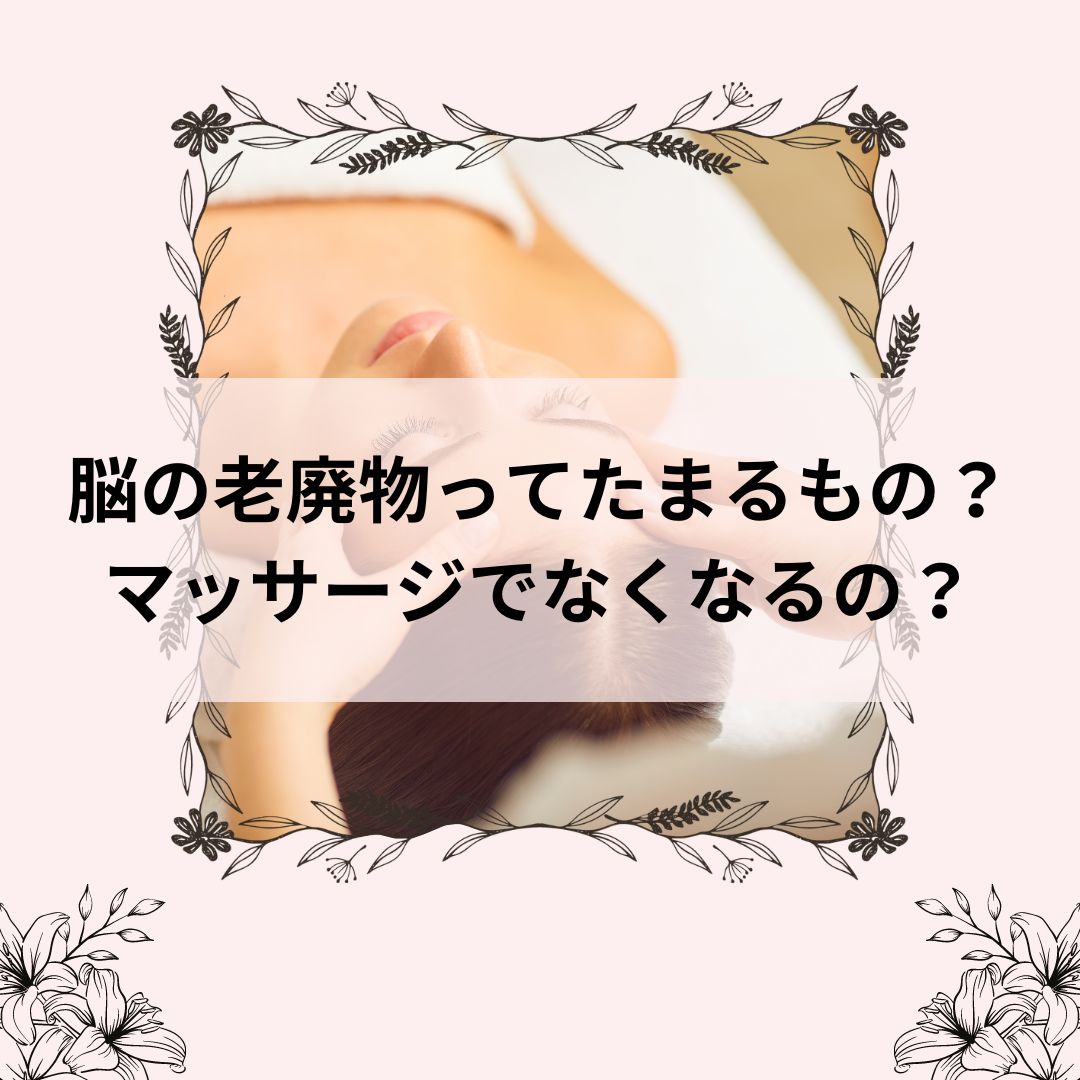あなたは登山が好きですか?
私は、運動慣れしていないせいか、登山後は疲労を感じやすくて、1度しか登山をしたことがありませんでした。
登山の疲労の原因は、乳酸(疲労物質)が身体から出てしまうことでした。
今回は、その詳しい原因について、回復方法、予防方法について紹介します。
あなたもこれを読んで、登山後の疲労について知りましょう。
登山での疲労について

あなたは、登山をすると疲労を感じますか?
私は学生のとき、友だちと登山をしたことがありましたが、下山後すぐに腕と足が筋肉痛になってしまいました。
この疲労は、乳酸(疲労物質)が身体から出てしまうことが原因でした。
乳酸は、運動をすることによって身体から出ると言われていますが、決してすべての運動に当てはまるとは限りません。
個人差はありますが、あなたの最大体力の60%以上で身体から出てしまいます。
例えば、ウォーキングの場合は最大体力の20%から40%とされています。
さらに、100m走の場合は、80%から100%ほどとされています。
つまり、普段のウォーキングでは乳酸は出にくいということになります。
乳酸を出さないようにする方法は、「相手に合わせて歩かないこと」です。
もし、相手のペースに合わせて登ってしまうと、無理をしたと同時に乳酸が身体から出てしまい、疲労を感じてしまいます。
反対に、登山のベテラン者は自分の最大体力を知っているため、自分に合ったペースで登り続けることができます。
ですが、登山のベテラン者のように自分の最大体力を知っていれば、疲労を感じないで済むと思いますが、簡単には身に付かないですよね?
そんなあなたのために、次は登山後の疲労回復方法について紹介します。
登山後の疲労回復方法

登山後に筋肉痛になったまま、学校や仕事に行くのは嫌ですよね?
ここからは、登山後の疲労回復方法について紹介します。
方法は全部で4つあります。まとめると以下の通りです。
・筋肉痛の部分を冷やす
・入浴
・タンパク質をたくさん摂る
・よく寝ること
どれも、登山後すぐにできることばかりですよね? 詳しく説明していきます。
・筋肉痛の部分を冷やす
登山後に温泉もいいですが、「冷やすこと(アイシング)」が疲労回復では大切です。
冷やすことは、血管を早めに収縮することができて筋肉痛の広がりを防ぐ効果があります。
もし、山の近くの温泉に冷水浴があったら、疲労を感じている脚から腰まで入れて冷やしましょう。
冷水浴がない場合は、冷たいシャワーで筋肉痛の部分を冷やすことも効果が期待できます。
山の近くに温泉がない場合は、帰りにコンビニなどで氷を買って冷やすこともできます。
・入浴
入浴も疲労回復に効果があると言われています。
近くに温泉があれば、温泉とそのプラスアルファの効能もあるのでおすすめです。
温泉がなくても、家の浴槽でも効果が期待できるので安心してください。
お湯の温度はあなたの好みで問題ありません!
また、冬に登山した後に入浴すれば、しもやけの予防にもつながります。
・タンパク質をたくさん摂る
筋肉痛からの回復で、食事、特にタンパク質はとても重要です。
タンパク質は、肉、魚、乳製品などです。その他にもアミノ酸やプロテインのサプリメントも積極的に摂りましょう。
また、登山は、長時間運動のため身体の中のグルコーゲンという物質がなくなってしまいます。
このグリコーゲンを補うことができれば、早めの疲労回復につながるので、ご飯や麺類などの糖質もタンパク質と一緒に採りましょう。
アルコールについては適量であれば疲労回復に効果があると言われています。
飲みすぎに注意すれば、登山後にお酒が飲めるのはいいポイントですね。
・よく寝ること
個人差はありますが、最低7時間以上の睡眠時間を確保すれば、疲労回復に効果が期待できます。
より睡眠の質を上げるには、「就寝直前に飲食をしない」、「寝る前にスマホを見ない」、「朝起きて日光を浴びる」、「湯船に浸かって体温を上げてから寝る」を心がけましょう。
その他の疲労回復方法は、疲労回復効果があるウェアやタイツなどもおすすめです。
例えば、ウェアは、体から出された熱を吸収して、それを再放射するといった機能で血流が改善することで、疲労回復が促されます。
タイツは、登山の帰りの電車や車の中で着用することで、ふくらはぎの筋肉痛をやわらげる効果があります。
登山での疲労回復にかかる日数は、個人差はありますが、ゆるい登山の場合はおよそ1日、ハードな登山の場合は、およそ2日から3日ほど、自分の限界を超えての登山の場合は、およそ4日から5日ほどかかります。
以上が、登山後の疲労回復方法についてでした。
どの方法も大切で、すべて取り入れたくなりました。特に食事についてはすぐにできそうだなと思いました。
あなたも参考にして、登山後に疲れない身体を手に入れましょう。
ですが、「回復方法はわかったけど、登山後に疲労を感じないように、予防する方法はないかな?」って思ってきませんか?
続いては、登山の疲労の予防方法について紹介します。
このまま読み進めてくださいね。
登山での疲労の予防方法

登山での疲労による筋肉痛を少しでも予防したいですよね?
予防方法は、前述した回復方法と筋トレとストレッチのです。
詳しく紹介します。
・筋トレ
筋肉痛の原因は、自分の最大体力を超えると起きやすいです。
そのため、登山前から自分の限界を超える日々の筋トレが予防につながります。
例えば、週2回から3回ほどおこなうのがおすすめです。
登山前からしっかりトレーニングをしていけば、登山中も登山後も筋肉痛にならない可能性があがります。
・ストレッチ
登山前と登山後にストレッチをしましょう。
泊りがけの登山でも、1日が終わった後にしっかりストレッチをしておけば、翌日の疲労をやわらげる効果が期待できます。
また、登山中も適宜ストレッチをしておくことも大切です。
ストレッチのコツは、勢いをつけずにゆっくり伸ばして、数十秒間姿勢をキープすることです。
特に登山後の入浴後にやると筋肉がほぐれやすくなっていて、効果も期待できます。
ちなみに、「マッサージは?」と思いますが、痛みがあるときにマッサージをしてしまうと、さらに痛みがひどくなることがあるので控えましょう。
以上が、登山での疲労の予防法についてでした。
回復方法にプラスして筋トレとストレッチも取り入れれば、ばっちり予防できそうですね。
あなたも、ぜひ試してみてくださいね。
まとめ

登山の疲労は、乳酸(疲労物質)が身体から出てしまうことが原因です。
乳酸を出さないようにするには、「相手に合わせて歩かないこと」がポイントです。
登山後の疲労回復方法は、「筋肉痛の部分を冷やす」、「入浴」、「タンパク質をたくさん摂る」、「よく寝ること」です。
また、登山での疲労の予防方法は、筋トレとストレッチです。
以上が、登山後の疲労回復に効く方法についてでした。
私は今まで、登山に対して苦手意識がありましたが、回復方法や予防方法を学んで、また挑戦したくなりました。
あなたも、この記事を読んで登山を始めてみませんか?